「袖ボタンって、3つ? 4つ? 正解ってあるんですか?」
スーツを仕立てる際、意外と迷うこの質問。
今回は、クラシックスーツの文脈と歴史のディティールをたどりながら、オーダースーツカマクラの視点でその“正解”を考えてみましょう。
■ そもそも「袖ボタン」って何のため?
現在では装飾的な意味合いが強くなっているスーツの袖ボタン。
しかし、かつては実用品でした。
元々は軍服の名残。特に有名なのが、イギリス近衛連隊の識別用として袖ボタンの数や配置が違っていたという事実。
つまり、連帯の区別をつけるための“印”だったのです。
袖ボタンの数と連隊名
1個
Grenadier Guards(グレナディア・ガーズ)
一番格式高く、王室警備を務める最上級連隊
2個
Coldstream Guards(コールドストリーム・ガーズ)
軍服起源は革命期、英国王室復帰後最初期に統合された連隊
3個
Scots Guards(スコッツ・ガーズ)
イングランドとスコットランド統合以降の伝統継承連隊
4個
Irish Guards(アイリッシュ・ガーズ)
アイルランド出身兵士を中心に編成された比較的新しい連隊
5個
Welsh Guards(ウェールズ・ガーズ)
20世紀に編成され、ウェールズを象徴する連隊
なぜボタンの数で判別するのか?
これらの袖ボタンは、各連隊の「識別マーク」としての機能があり、近衛連隊のステータスを示す重要なクラシックディテールでした。
連隊ごとに1~5個のボタン数が異なることで、**軍服の混同を防ぐための“コード”**だったと言われています
ナポレオンの説
ナポレオンが兵士たちの鼻水拭きを防ぐために付けたという説は有名ですが、これは史実としては誤り。
真実はもっと“クラシックで機能的”。
整列・区別・格式を示すために、ボタンの数には明確な意図が込められていたのです。
■ 1950年代クラシックスーツの“正解”は?
オーダースーツカマクラが愛する1950年代のクラシックスーツでは、3つボタンが主流でした。
この時代は、まだ軍服の名残を引きずりながらも、市民の服として成熟し始めた時代。
袖ボタンもただの飾りではなく、「きちんと感」や「均整美」の象徴として重要視されていました。
また、ヴィンテージのスーツを観察すると、3つ配列の美しさや、角度をつけて重ね気味に配置するスタイルなど、意外と奥が深いのがわかります。
■ 「4つボタン」は間違いなのか?
いいえ、そうではありません。
現代的なスーツでは4つボタンがスタンダードになっているケースも多く、これ自体が間違いというわけではないのです。
ただし、**スーツの雰囲気や時代背景に合わせてボタン数を選ぶのが“粋”**というのが、オーダースーツカマクラの考え方。
私たちは、袖ボタンひとつ取っても**「何のためにその数なのか」**を明確にした上で提案します。
■ 結論:「正解」は、時代とスタイルに宿る
ボタンの数に“唯一の正解”はありません。
しかし、そのスーツが宿す時代背景や精神性にふさわしい数は、確かに存在します。
オーダースーツカマクラでは、そうした**「背景のあるディティール」**を重視し、お客様のスーツに魂を込めて仕立てています。
世田谷を拠点に、出張採寸専門だからこそできる、対話と再現性のあるスーツづくり。
袖ボタンひとつにもストーリーと連帯感を宿す。
それが、私たちのクラシックスーツです。
「なんとなく」で選ばない。袖ボタンひとつにも“意思”を宿す。そんなスーツを、一緒に作りませんか?
スーツでも活きるクラシックディテール
Order Suit KAMAKURAでは、こうした歴史あるディテールをスーツに落とし込むことを大切にしています。
袖ボタンの数や配置にも背景があり、ただ飾りではなく意味を持つ装いを現代のビジネススーツにも継承しています。
袖ボタンひとつで、スーツが語る歴史と格式が変わります。
近衛連隊由来のディテールを知ることで、自分の着こなしに深みと品格を加える――
そんなクラシック回帰が、令和のビジネススタイルでも光ります。
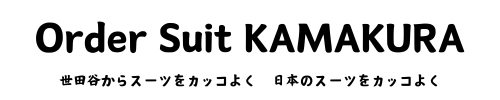



コメント